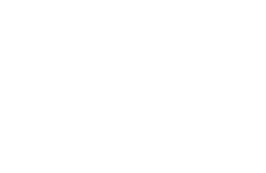脱炭素社会に向けて
2020年10月26日、第203回臨時国会の所信表明演説において、菅義偉内閣総理大臣は「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする(※)、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。
※「排出を全体としてゼロ」とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収量を差し引いた、実質ゼロを意味しています。
我が国は、現在、年間で12億トンを超える温室効果ガスを排出しており、2050年までに、これを実質ゼロにする必要があります。
このカーボンニュートラルへの挑戦が、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想で、日本全体で取り組んでいくことが重要です。
環境省では、新たな地域の創造や国民のライフスタイルの転換など、カーボンニュートラルに向けた需要創出の観点に力を入れながら、政府一丸となって取組を推進しています。 環境省:脱炭素ポータルより引用

脱炭素に向けて、国が率先して動いています。そして、地球温暖化対策新進法の一部改正案が令和3年5月26日に設立しました。
温暖化への対応は経済成長の制約ではなく、積極的に温暖化対策を行うことが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要です。
その為に我々ができる事として、太陽光、蓄電池などの再生可能エネルギーの普及。カーボンニュートラルの実現には再生可能エネルギーの利用が不可欠です。地方創生につながる再エネ導入を促進していきます。

植樹による大気中の二酸化炭素を減らす運動
木は光合成によって、葉の気孔から二酸化炭素を取り入れ、根から水を吸い上げ、葉緑素の働きと太陽の光エネルギーを利用して、ブドウ糖(グルコース)を作り酸素を放出します。
生成されたブドウ糖を基にして樹体を形成するための成分のセルロース、ヘミセルロース、リグニンが作られ木が大きくなります。
木の元素構成は、炭素約50%、酸素約44%、水素約6%およびその他となっています。
したがって、木は植えられてから成長している間、大気中から二酸化炭素を吸収し、炭素として固定し、大気中の二酸化炭素を減らし続けてくれます。


昨今では、テレビやネットニュースなどで耳にする事が多くなったSDGsへの同意のみならず、ESGの重要性にフォーカスする事も必要だと考えています。
EGSとは
環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)
の頭文字を取った言葉です。